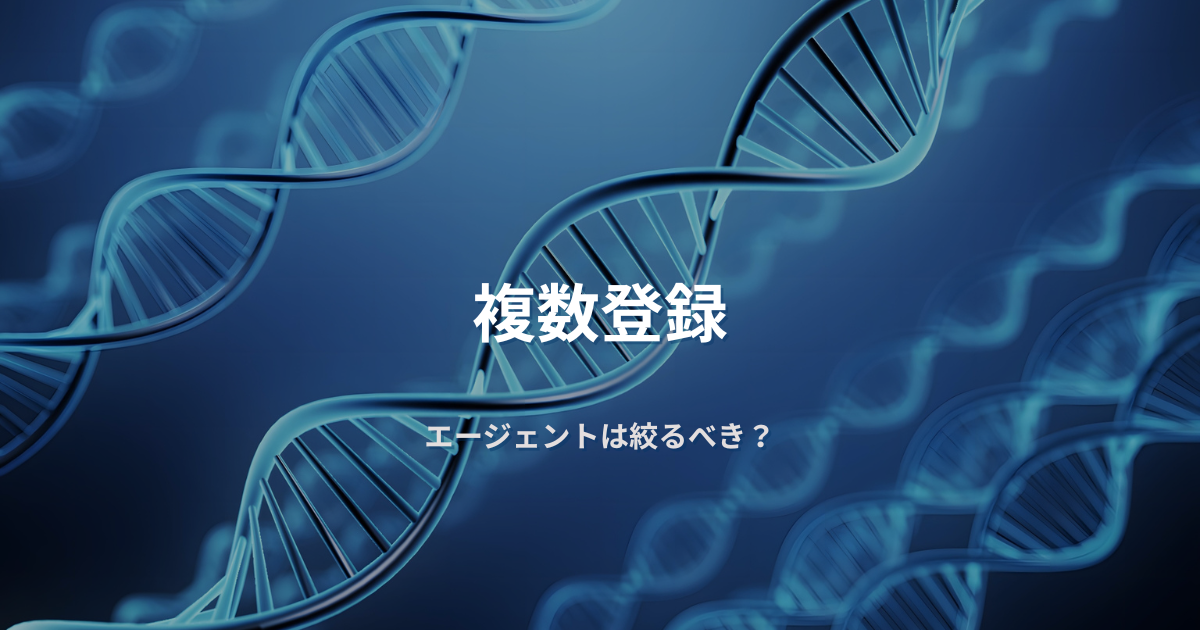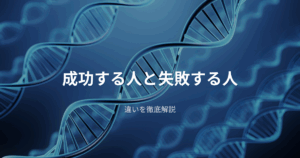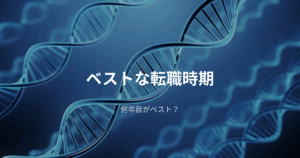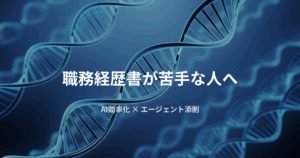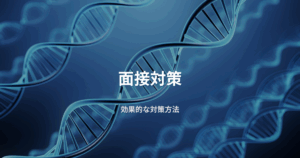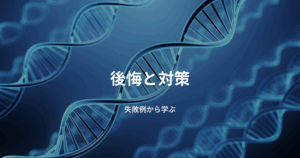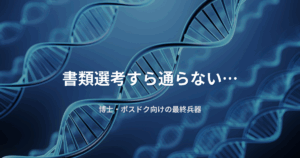「転職エージェントって複数登録した方がいいのかな…?」「何社ぐらい登録すべきか分からない…」
そんな悩みを抱える方は少なくありません。
転職活動では、エージェントをどう使うかによって得られる求人やサポートの質が大きく変わります。特に「登録数」は転職の成功率に直結する重要なポイントです。
- 転職エージェントは複数登録すべきかどうかが分かる
- 何社登録すれば効率的か、その目安を知れる
- 複数登録のメリット・デメリットを理解できる
- 自分のキャリアに合ったエージェントの組み合わせ方を学べる
 とあぱぱ
とあぱぱ私自身も転職活動の際に「1社で十分なのか?」「複数登録した方がいいのか?」と迷いましたが、実際に複数のエージェントを併用したことでサポートの質や求人の幅に大きな差が出ることを実感しました。特に、担当者との相性や非公開求人の有無は、1社だけでは気づけないポイントです。この記事では、その経験も踏まえながら「何社登録すべきか」「どう使い分けるべきか」を分かりやすくお伝えします。
この記事を読むことで、転職エージェントを複数登録すべき理由 と 登録数の目安 が理解できます。さらに、メリット・デメリットや注意点も整理できるので、効率よく転職活動を進める具体的なヒントを得られるはずです。
研究職でまず登録すべきはこの3社!


大学院生・ポスドクに特化


関西メーカーの非公開求人に強い


業界最大40万件以上
転職エージェントは複数登録すべき?【結論】


結論から言うと、転職エージェントは2〜3社の複数登録がおすすめです。1社だけでは担当者との相性や紹介される求人に偏りが出やすく、機会を逃してしまうリスクがあります。
リクルートやdodaなど大手の調査によれば、転職成功者の多くは 平均2.5社前後のエージェントに登録しています。これは「複数社を比較しながら、自分に合った担当者や求人を選んでいる」結果といえます。
1社だけでは損するケースが多い
転職エージェントを1社に絞って活動する人もいますが、実は大きなリスクがあります。エージェントはそれぞれ得意分野や強みが異なり、担当者の対応力や保有している求人の質はバラつきがあるためです。
- 担当者との相性が合わないとサポートが十分に受けられない
- エージェントごとに保有している求人が異なるため、1社では求人の幅が狭くなる
- 他社にしかない独占案件(非公開求人)を見逃す可能性がある
つまり、1社だけでは効率的に思えても、結果的に 求人の幅やサポートの質が制限されてしまい、転職の成功率を下げる可能性があるのです。
複数登録する人の割合・平均登録数
では実際に、転職経験者はどのくらいの数のエージェントに登録しているのでしょうか。アンケート調査のデータを見てみると、複数登録が一般的 であることがわかります。
| 転職エージェントの社数 | 割合 |
|---|---|
| 1社 | 26.6% |
| 2社 | 33.1% |
| 3社 | 26.1% |
| 4社 | 7.0% |
| 5社 | 7.0% |
| 6社以上 | 0% |
転職経験のある人たちは、実際に何社の転職エージェントを利用したのでしょう。「就職活動で転職サイト・エージェントはいくつ登録しましたか?」というアンケート結果(グラフ参照)によると、登録した転職サイト・エージェントの社数は、「2社」という回答がもっとも多く、33.1%を占めています。「3社」は26.1%。「4社」「5社」の回答もありますが、6社以上はありませんでした。
「1社」と答えた人は全体の26.6%にとどまり、転職経験者の多くが転職エージェントを複数利用していることがわかります。平均の登録社数は、2.3社という結果でした。出典:リクルートエージェント
このデータからも分かるように、もっとも多いのは2社登録(33.1%)、次いで3社(26.1%) でした。平均登録数は 2.3社 と出ており、多くの人が2〜3社を併用して転職活動を進めていることが分かります。つまり、「複数登録が基本」かつ「2〜3社がベスト」 というのが実態といえます。
転職エージェントは何社登録がベスト?
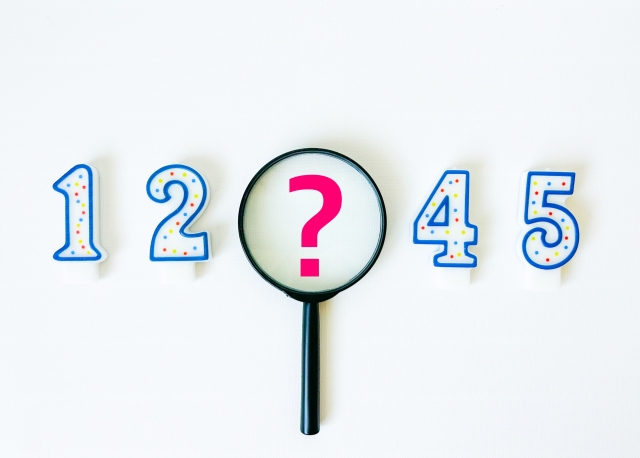
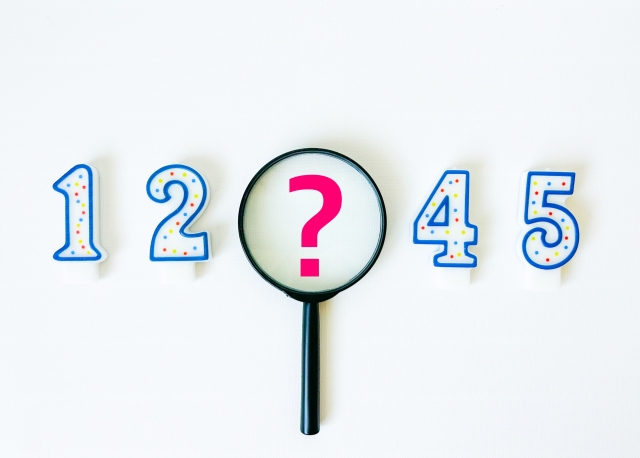
転職エージェントは、効率と情報量のバランスを考えると 2〜3社程度の登録がベストです。1社だけでは求人やサポートの幅が狭まり、逆に5社以上になると管理が煩雑になりがちです。
まずは 大手1社+特化型1〜2社 を目安に登録してみると、無理なく情報を得ながら効率的に活動できます。
最適な登録数は2〜3社
では、なぜ2〜3社がちょうど良いのでしょうか? その理由は大きく3つあります。
- 求人の幅を広げられる
- 大手総合型エージェントでは幅広い求人を、専門特化型ではニッチで高精度な求人を探すことができます。両方を組み合わせれば、選択肢を広げつつ質も確保できます。
- 担当者を比較できる
- サポートの丁寧さや提案力、面接対策の具体性などは担当者によって差があります。2〜3社に登録すれば「自分と相性の良い担当者」を見極めやすくなります。
- 情報管理がしやすい
- 4社以上になるとメールや面談日程の調整で混乱しやすくなります。2〜3社であれば、無理なく情報を整理しながら効率よく転職活動を進められます。
このように、2〜3社なら「求人の幅」「担当者の相性」「効率的な管理」のすべてを両立でき、最も実用的な登録数といえます。
4社以上は情報収集に役立つがデメリットも
「もっと幅広く求人を見たい」「担当者との相性を見極めたい」という方は、4社以上に登録するのも一つの方法です。
ただし、連絡や面談の回数が増えすぎると転職活動が少し忙しくなります。
- スケジュール管理が大変になる
- 同じ求人を複数のエージェントから紹介される
- 担当者への対応に追われてしまう
このようなデメリットが生じる点には注意が必要です。
転職エージェントを複数登録するメリット
転職エージェントを複数登録すると、1社だけでは得られない多くのメリットがあります。特に転職活動の成功率を高めるうえで、大きな効果をもたらすのが次の3点です。
比較することで担当者の質を見極められる
転職活動において担当者との相性は非常に重要です。転職エージェントの担当者も人間なので質の高さや話やすさはどうしても個人差が出る部分となります。
- 親身に相談に乗ってくれるか
- 提案する求人が自分の希望に合っているか
- 面接対策や書類添削の具体性
こうしたサポートの質は担当者によって大きく異なります。複数登録して比較することで、信頼できる担当者に出会える確率が高まります。
求人情報の幅が広がる
転職エージェントは、それぞれ独自の求人を保有しています。1社に絞ると、他社にしかない「非公開求人」や「独占案件」を見逃すリスクがありますが、複数登録すればその心配は軽減されます。
さらに、エージェントごとに運営の仕組みが異なることも知っておきたいポイントです。
- 分業型(リクルートエージェントなど)
- 「求職者担当」と「企業担当」が分かれており、求職者担当はあなたの希望を深く理解し、企業担当は採用企業の情報を提供します
- 両面型(JACリクルートメントなど)
- 一人の担当者が企業を中心に担当し、求職者も担当するスタイルで、企業側のニーズに精通しているのが特徴です。
このように、エージェントによって求人の持ち方やサポートの仕組みが大きく異なるため、複数登録することで幅広い情報を得られるだけでなく、違った視点の提案を受けられるというメリットもあります。
選考対策の視点が増える
転職エージェントごとに得意分野やサポートのスタイルが異なるため、複数登録することで多角的なアドバイスを受けられます。大きく分けると、次のようなタイプがあります。
- 大手総合型エージェント(例:リクルートエージェント、doda)
企業ごとの選考傾向や過去の面接事例に詳しく、豊富なデータをもとにした対策が強みです。 - 業界・職種特化型エージェント(例:アカリクキャリア、メイテックネクスト)
特定の業界に特化しているため、専門用語や業界事情を踏まえた具体的なアドバイスを得られます。 - ハイキャリア・外資系向けエージェント(例:JACリクルートメント、ロバート・ウォルターズ)
企業との密接なつながりを活かし、役職や待遇など条件交渉を含めた実践的なサポートを受けやすいのが特徴です。
このように、複数のタイプを併用することで「幅広い面接ノウハウ」+「業界特化の知見」+「ハイキャリア視点の助言」を組み合わせられ、より実践的で質の高い準備ができます。
転職エージェントを複数登録するデメリットと注意点
複数登録には多くのメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。事前に理解しておけば、効率的に活用できます。
複数のエージェントと同時にやり取りすると、面談日程が重なったり、メールが埋もれてしまうことがあります。予定が錯綜すると、選考準備にも影響が出やすくなります。
✅ 対策: Googleカレンダーやタスク管理アプリに「エージェント名+内容」で登録しておきましょう。面談は同じ曜日・時間帯に集約すると混乱を防げます。
同じ求人を複数のエージェントから紹介されるケースは珍しくありません。応募窓口が分散すると、進捗が追いづらく、企業側にも二重応募のリスクを与えてしまいます。
✅ 対策: 応募管理用のスプレッドシートを作成し、「企業名/職種/紹介元エージェント/応募日/選考状況」を一覧化しましょう。同じ求人は1つの窓口に統一するのが鉄則です。
エージェントごとに定期的な連絡やヒアリング依頼があるため、複数社に登録すると応答負担が増えます。結果的に、本命の選考準備が疎かになるケースもあります。
✅ 対策: メイン1社+サブ1〜2社の役割を明確にしましょう。メインには深い相談、サブには求人紹介メインと役割分担をすると、無理なく対応できます。
希望条件やNG条件をエージェントごとに伝え忘れると、求人紹介の精度が落ちたり、認識のズレからミスマッチが起きやすくなります。
✅ 対策: 希望条件は「必須/歓迎/NG」に分けてテンプレート化し、全エージェントに同じ資料を共有しましょう。更新も必ず同一ファイルだけにまとめることで情報ブレを防げます。
転職エージェントを複数登録するときの上手な使い方


複数登録はメリットが大きい反面、使い方を間違えると情報過多で混乱してしまいます。ここでは、効率よく活用するためのコツを紹介します。
メイン・サブのエージェントを決める
複数登録したら、最初に 「軸になるエージェント」と「補助的に使うエージェント」 を決めましょう。
- メイン:信頼できる担当者がついた会社。書類添削や面接対策などの伴走支援を依頼
- サブ:求人の情報収集や比較用。条件を広げて見たり、違う切り口の提案をもらう
同じ求人に複数応募しないよう注意
複数登録で一番多い失敗が「同じ求人に二重応募」してしまうことです。企業からすると「管理ができていない応募者」と見られ、印象が悪くなるリスクがあります。
応募管理表(Excel、スプレッドシート) を作り、以下を一覧にしておくと重複を防げます。
- 企業名
- 職種名
- どのエージェント経由か
- 応募日/選考状況
仕組みの違いを活かす
先ほども述べた通り、エージェントには大きく2つの仕組みがあります。
- 分業型(例:リクルートエージェント、doda)
求職者担当と企業担当が分かれているため、求職者の希望を深く理解してもらいやすい。 - 両面型(例:JACリクルートメント)
一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当。企業の内部事情に詳しく、条件交渉にも強い。
おすすめの転職エージェント登録組み合わせ【タイプ別】
複数登録するときは、ただ有名なところに片っ端から登録するのではなく、役割が異なるエージェントを組み合わせることが重要です。ここでは目的に応じたおすすめの組み合わせ例を紹介します。
・リクルートエージェント/doda(大手総合型)
→ 幅広い求人と安定したサポート体制が魅力。
・アカリクキャリア(理系院卒向け)/メイテックネクスト(技術職特化)(専門特化型)
→ 自分のキャリアに直結する専門求人をカバー。
💡 総合型で全体を押さえつつ、特化型で専門分野を深掘りするのが王道です。
JACリクルートメント(ハイキャリア)
→ 管理職・専門職・外資系に強く、企業と直接つながる「両面型」のサポート。
パソナキャリア/MS-Japan(キャリア支援型)
→ 30代以降の転職に手厚いサポート。キャリアチェンジや年収アップ交渉に強い。
💡 「今の経験を活かしつつ、次のステージへキャリアを伸ばしたい30〜40代」におすすめの組み合わせです。
ヒューレックス/リージョナルキャリア(地域密着)
→ 地元企業やU・Iターンに特化。
パソナキャリア/Spring転職エージェント(全国型)
→ 全国規模のネットワークで幅広い選択肢を確保。
💡 地域で働きたい人が「地元の強み」と「全国的な求人」を両立できる形です。
このように、「大手+特化」「ハイキャリア+若手」「地域+全国」といった組み合わせを意識すると、求人の幅を広げつつ自分のキャリアに合った情報を得られます。
まとめ|転職エージェントは複数登録で相性を見極めよう
転職エージェントは 2〜3社の複数登録がベスト です。1社だけでは求人や担当者の幅が狭くなり、逆に多すぎると管理が難しくなるため、まずは「大手総合型+特化型」や「ハイキャリア型+キャリア支援型」など、役割を分けた組み合わせで始めるのがおすすめです。
- メインとサブを決めて役割分担する
- 同じ求人に複数応募しないよう管理する
- エージェントの仕組みの違いを活かす
30〜40代の転職は、これまでの経験をどう活かすかが成否を分けます。だからこそ、複数のエージェントを比較し、自分と相性の良い担当者を見つけることが成功への近道です。
転職は人生の大きな節目です。複数登録をうまく使いこなし、自分にとって最適なキャリアの一歩を踏み出してください。
🔗 具体的なエージェントの特徴や評判はこちらの記事で詳しく解説しています。
研究職でまず登録すべきはこの3社!


大学院生・ポスドクに特化


関西メーカーの非公開求人に強い


業界最大40万件以上
Q&A
転職エージェントは複数登録すると企業に悪印象を持たれませんか?
基本的に悪印象にはつながりません。むしろ転職希望者が複数の情報源を持っているのは自然なことです。注意すべきは 同じ求人に複数応募しないこと。二重応募は企業に不信感を与えるため、応募窓口は必ず一つに絞りましょう。
転職エージェントは何社まで登録していいの?
登録自体に上限はありませんが、効率よく活用できるのは2〜3社 です。4社以上になるとスケジュール調整や情報整理の負担が増え、結局活かしきれないケースが多くなります。
30〜40代で複数登録するなら、どんな組み合わせがいい?
ミドル層には 「大手総合型+ハイキャリア型」、または 「大手総合型+専門特化型」 の組み合わせがおすすめです。
例)リクルートエージェント+JACリクルートメント、または doda+アカリクキャリア。
キャリアの幅と専門性の両方を押さえられるので、求人の選択肢が広がります。
複数登録するときに最も注意すべきことは?
一番の注意点は 情報管理の徹底 です。応募状況や面談日程を整理しないと混乱してしまいます。Googleスプレッドシートやカレンダーを使って「企業名/応募日/経由エージェント/進捗」を一覧化するのがおすすめです。
エージェントを途中で変更・解約しても大丈夫?
「もちろん可能です。エージェントに費用はかかっていないので、合わないと感じたら早めに利用をやめてOK。特に30〜40代は時間が貴重なので、「相性が良いかどうか」を見極め、必要に応じて入れ替えるのが効率的です。