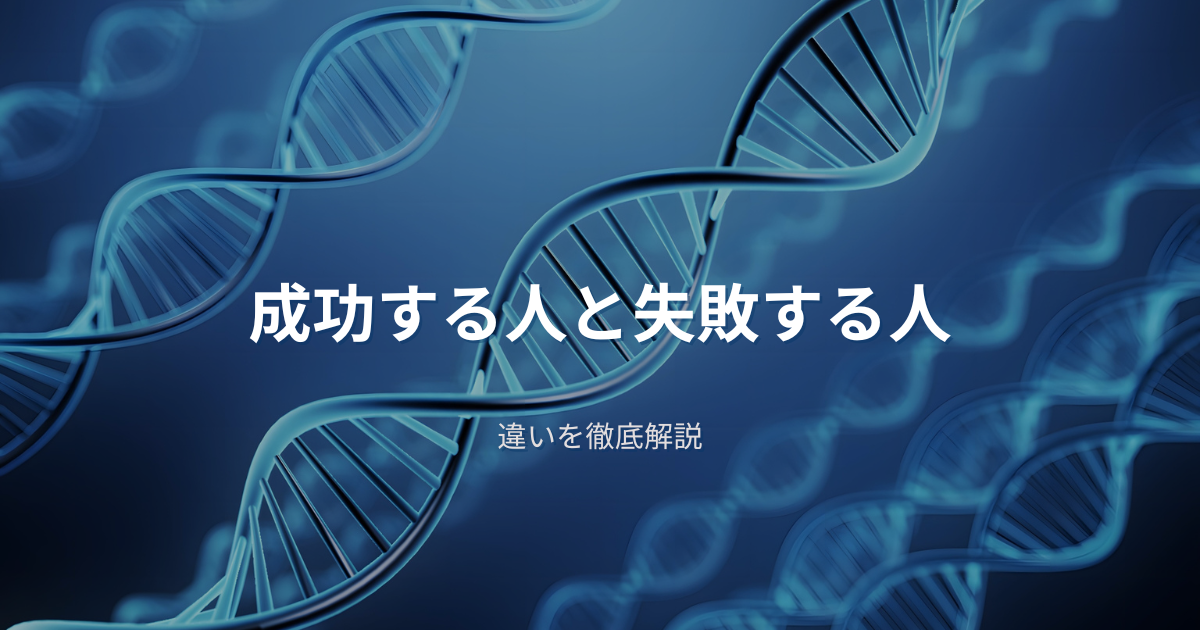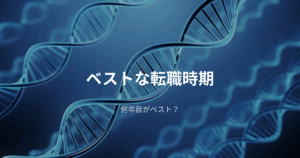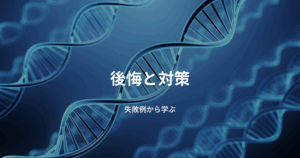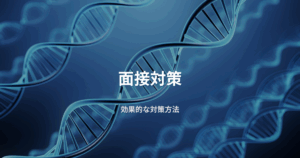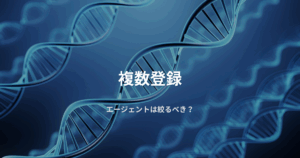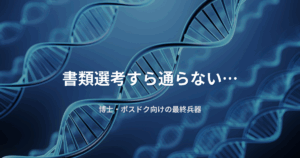【PR】本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。リンク経由で成約があった場合、当サイトに収益が発生することがあります。ただし、掲載する転職エージェントの選定・評価は筆者の経験と独自の基準に基づいています。
「研究職として働いているけれど、転職を考えると不安…」
そんな声をよく耳にします。研究職は専門性が高く、求人の数も限られているため転職が難しいと言われることが少なくありません。
本記事では、研究職が転職しにくい理由を整理し、成功する人・失敗する人の違いを具体的に解説します。
自分はどちらのタイプに当てはまるのかを確認しながら読むことで、今後のキャリア戦略を考えるヒントが得られるはずです。
- 研究職の転職がなぜ難しいのかを知りたい
- 研究職で転職に成功する人の共通点を知りたい
- 逆に転職に失敗してしまう人の特徴を知りたい
- 研究職から転職を成功させる具体的な方法を知りたい
 とあぱぱ
とあぱぱ研究職からの転職を考えるとき、スキルや経歴だけでなく「伝え方」や「戦略」が大きく結果を左右します。私自身も研究開発職のキャリアを歩んできた中で、成功例・失敗例の両方を見てきましたが、ちょっとした準備の差が大きな結果の違いを生んでいました。
この記事を読むことで、研究職の転職が難しいと言われる背景と、成功・失敗を分ける分岐点が理解できます。さらに、最後には転職を成功に導く具体的なポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
研究職でまず登録すべきはこの3社!


大学院生・ポスドクに特化


関西メーカーの非公開求人に強い


業界最大40万件以上
研究職の転職を考えるなら、まずは情報収集が重要です。詳しくは以下の記事でまとめています。


研究職の転職はなぜ難しい?【4つの理由】


求人数が少なくポストが限られている
研究職は、欠員補充や新規テーマの立ち上げ以外で募集が出にくく、さらに分野や役割ごとに細分化されているため希望に合う求人が少ないのが現状です。
- 今のチームにすぐ馴染み、既存テーマを前に進められる人材
- 限られたポストに「即戦力」として適合できる人
- 求人が出るまで待ち、募集開始時には競争が激化してしまう
- 「研究なら何でもやります」と広すぎる志望で専門性が伝わらない
👉 母集団が小さく、採用要件も狭い。だからこそ情報の先取りと適合の言語化が勝負。
専門性がニッチで応用が難しい
研究スキルは装置や材料など固有の専門領域に偏りがちで、そのままでは他社や他業界へのアピールに繋がりにくい傾向があります。
- 「専門技術が事業にどう貢献するか」を理解して説明できる人
- 手法や知識を新しいテーマに応用できる柔軟性
- スキルを手法名の羅列で終わらせてしまう
- 自分の専門を守る説明ばかりで、「企業でどう活かせるか」が抜ける
👉 ニッチは武器にも弱点にもなる。専門を“事業価値”に変換できる人が一歩抜けます。
アカデミア経験の評価が分かれる
論文・学会発表は強みですが、企業は「期限・コスト・チーム連携」の中で成果を出せるかを重視します。ポスドク歴が長い場合などは、産業側に寄せた表現ができないと懸念を持たれやすいです。
- 制約条件(納期・予算・品質基準)を踏まえて成果を出せる人
- 開発プロセスの中で次工程(試作・量産・薬事など)に橋渡しできる人
- 共同研究や社内外の調整に強みを持つ人
- 論文実績やインパクトファクターに偏った自己PR
- 「自由探索型研究」から「事業開発型研究」への適応を示せない
👉 アカデミアの強みは活きる。鍵は企業文脈への“翻訳”とプロセス適応性の証明。
年齢が上がるほどハードルが高くなる
30代後半以降は、実験スキルだけでなく「チームを前進させる力」やマネジメント経験が期待されます。給与レンジや勤務地の条件も、選考でシビアに見られがちです。
- 若手研究者の育成や技術指導を担える人
- プロジェクト推進・意思決定・リスク管理の経験がある人
- 研究を事業へと橋渡しできる視点を持つ人
- 個人スキルだけに依存した自己PR
- 給与・勤務地条件を最初から絞りすぎて機会を狭めてしまう
👉年齢=不利ではない。役割期待(推進・育成・横断)に応える証拠を出せるかが鍵。
研究職の転職で成功する人の特徴


スキルを「事業貢献スキル」として言語化できる
研究者は技術や知識を説明しがちですが、企業が知りたいのは「売上や事業貢献にどう繋がるか」です。たとえば「HPLCでの分析経験」ではなく「品質問題を特定し、出荷停止を回避した」と言える人は評価されやすくなります。専門性を成果や価値に翻訳できることが、転職成功の第一歩です。



今持っている技術や知識を、応募先企業でどう活かせるかを面接官にイメージさせることが大切だと思います。
企業ニーズや業界動向をリサーチしている
成功する人は、自分の専門を一方的に売り込むのではなく、企業が今後求める研究テーマや市場ニーズを調べた上で応募しています。たとえば「食品企業が腸内細菌研究に投資している」「製薬業界がデータサイエンス人材を求めている」など、業界トレンドを把握してアピールすることが強みになります。



企業や業界の分析も重要ですが、私が最も意識したのは「求人内容」の深掘りでした。やりたいことを語るよりも、求人票に書かれた人物像へのフィット感を示すだけで通過率が大きく変わりました。
コミュニケーション力・マネジメント経験がある
近年の研究はチームで動くため、異なる専門を持つ人と協働し成果を出す力が重視されます。また30代以降になると、若手の育成や外部パートナーとの折衝経験を持つことが評価につながります。「専門家」から「推進役」へシフトできる人が成功しやすいです。



私はこの部分は得意ではありませんでしたが、代わりに知財やマーケ、生産技術など多部署と連携した経験をアピールしました。組織横断で動いた実績も十分評価対象になります。
転職エージェントを有効に活用している
成功している人の多くは、研究職に強い転職エージェントをうまく活用しています。非公開求人へのアクセスや職務経歴書の添削、面接対策を通じて、自分の強みを“企業が欲しい形”に変えて発信できているからです。情報収集の効率化と書類通過率の向上につながり、結果的に成功確率が上がります。



利用しないデメリットはないと思います。私は過去の面接内容や他応募者の状況まで共有してもらえました。基本的にエージェントとはwin-winの関係になるので、登録しない手はないです。
成功している人の多くはエージェントを味方につけています。比較記事はこちらをご覧ください。


研究職の転職で失敗する人の特徴


専門性に固執しすぎて選択肢を狭めてしまう
研究分野に強みを持つことは重要ですが、「この手法・この材料以外はやりたくない」という姿勢は企業に柔軟性の欠如と映ります。
- 「新しいテーマに適応できないかも」
- 「研究所内での配置転換が難しそう」
- 求人の母数が少ないのに、さらに可能性を自分で狭めてしまう
- 「守りの姿勢」が強調されてしまい、即戦力感が薄れる



私も初期は専門分野にこだわりすぎていました。ですが求人票に書かれている人物像に自分を寄せて説明することで、選考通過率が大きく上がりました。
志望理由が「研究を続けたい」だけで浅い
「研究を続けたい」という思いは自然ですが、それだけでは採用担当者に響きません。企業は事業成長のためにどう貢献できるかを求めています。
- 「自分のやりたいことが優先で、事業理解が浅い」
- 「会社にフィットするイメージが湧かない」
- 動機が抽象的すぎて、説得力が弱くなる
- 面接で「なぜ当社なのか」に答えられない



志望理由は「研究を続けたい」ではなく、企業が解決したい課題にどう貢献できるかを具体的に語ることが重要だと痛感しました。
業界研究・企業研究が不足している
採用側からすると「うちの事業や研究領域をどれだけ理解しているか」は強い関心事項です。ここが弱いと、即戦力性や熱意に疑問を持たれてしまいます。
- 「他社でもいいと考えているのでは?」
- 「長期的に働いてくれるイメージが持てない」
- 面接での回答が一般論にとどまり、印象が薄い
- 自分のスキルをどう事業に活かせるかが語れない



私は企業研究が苦手でしたが、生成AIを使うことで効率的に情報を収集し、本業をしながらでも対策をしていました。
40代以降で準備不足のまま転職活動を始める
年齢が上がるほど期待される役割は「リーダーシップ」や「横断的な推進力」です。準備不足のまま活動を始めると、即戦力性を疑問視されやすくなります。
- 「マネジメントや後進育成ができるか不安」
- 「給与レンジに見合う成果を出せるか疑問」
- 自己PRが実験スキルに偏りすぎて役割期待に応えられない
- 給与・勤務地条件を固めすぎて応募先を狭めてしまう



年齢が上がるほど、即戦力スキル+チームを動かした経験を語れるかが鍵だと思います。
失敗例に当てはまるかも…と感じた方は、まずはこちらを参考にしてみてください。
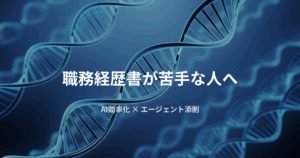
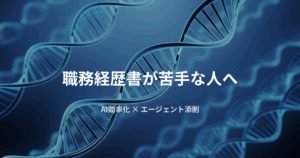
研究職が転職を成功させるための対策法


研究スキルを「企業が求める言葉」に翻訳する
企業が知りたいのは「どんな装置を使えるか」ではなく、そのスキルでどんな成果を生み出せるかです。
たとえば「細胞培養技術」ではなく「培養条件を最適化し、実験再現性を30%改善した」と伝えると効果的。



求人票の応募要件は要チェックです。必須条件に書かれている項目について、自分のスキルや経験を1対1で当てはめて語れるようにするのが大切。なぜなら、それこそが企業が求める条件を端的に表している部分だからです。
研究以外の経験(チーム成果・横断プロジェクト)を強調する
研究だけでなく、他部署との連携やプロジェクト推進経験も評価対象です。知財・生産技術・マーケティングなどとの協業経験をアピールすると「事業貢献できる人材」と認識されやすいです。



私はこの点は得意ではありませんでしたが、多部署と協力して成果を出した経験を強調したことで、評価が高まりました。
異職種(データサイエンス・知財・開発職など)も視野に入れる
「研究職」にこだわりすぎず、知財、品質保証、データサイエンスなど周辺領域を視野に入れることで可能性が広がります。実際に研究経験をベースにキャリアチェンジしている人も多く、長期的なキャリア設計に繋がります。



求人票をよく読むと、研究経験を評価しながら異職種を募集しているケースもあります。柔軟に選択肢を広げることで可能性が広がりました。
失敗例に当てはまるかも…と感じた方は、まずはこちらを参考にしてみてください。


研究職に強い転職エージェントを活用する
エージェントは求人紹介だけでなく、職務経歴書の添削、面接対策、非公開求人の情報提供までサポートしてくれます。特に研究職は求人が限られるため、専門性に強いエージェントを活用することで、効率的に選考を進められます。



私の場合は、自分では気づかなかった強みを指摘してもらえたのが大きかったです。求人票と照らし合わせながら「ここをもっとアピールすべき」と具体的に指導してくれるので、自己分析だけでは得られない気づきをもらえました。
転職の成功はエージェント選びで決まります。こちらの記事も参考にしてみてください


まとめ
研究職の転職は「求人が少ない」「専門性がニッチ」「アカデミア経験の評価が割れる」「年齢が上がるほどハードルが高い」といった要因から難しいのは事実です。しかし、成功する人と失敗する人の違いは明確であり、スキルの翻訳力・企業理解・横断的な経験・情報収集力といった工夫で大きく差がつきます。
転職活動を成功に導くためには、求人票を深掘りして企業の求める人物像にフィットさせる意識と、研究職に強い転職エージェントの活用が欠かせません。まずは自分の強みを整理し、次のステップとしてエージェント相談に進むのがおすすめです。
私自身もエージェントを活用したことで効率的に情報を集め、複数の内定を得ることができました。
研究職でまず登録すべきはこの3社!


大学院生・ポスドクに特化


関西メーカーの非公開求人に強い


業界最大40万件以上
Q&A
研究職の転職は何歳まで可能ですか?40代や50代でもチャンスはありますか?
研究職の転職に年齢制限はありません。ただし30代後半からは「マネジメント経験」や「横断的な推進力」が重視され、40代以降は後進育成やリーダーシップの実績が評価されやすくなります。50代でも専門性と実績次第で可能ですが、管理職ポジションやプロジェクト推進役としての採用が中心になります。
アカデミア(大学・ポスドク)から企業研究職に転職できますか?
可能です。実際に多くのポスドク研究者が企業研究職へ移っています。ポイントは、論文や学会実績だけでなく、「制約条件の中で成果を出した経験」や「共同研究・チームでの成果」を企業文脈に翻訳して伝えることです。産業界での再現性・納期・コスト意識を意識すると評価されやすくなります。
研究職から異職種(知財・品質保証・データサイエンスなど)にキャリアチェンジできますか?
できます。研究職で培った分析力・論理的思考・実験計画力は他職種でも高く評価されます。特に需要があるのは、知財(特許調査・明細書作成)、品質保証(規格適合・不具合解析)、データサイエンス(AI・統計解析)、開発職(商品企画・応用研究)です。求人票に「研究経験歓迎」とあるポジションを狙うと成功しやすいです。
研究職の転職は難しいとよく聞きますが、本当に無理なのでしょうか?
決して無理ではありません。難しいとされるのは「求人数が少ない」「専門性がニッチ」「年齢が上がると役割期待が変わる」ためです。しかし、スキルを事業貢献に翻訳する力・求人票を意識した準備・エージェント活用で成功している人は多くいます。